
今週の11月12日、東急不動産がオープンした「ビジネスエアポート東京 遊学堂」のオープニングセミナーとして、相模屋食料の鳥越淳司社長を招き「『ザクとうふ』の哲学」が開催されました。都心にできた注目のシェアオフィスのイベントということもあり、私も参加してきました。
で、これがとても面白い内容でだったので簡単にレポしておきます。
◎9年間で売上高が約5倍に成長!
相模屋食料は「ザクとうふのヒットで伸びた会社」というイメージが持たれがちですが、それは間違いで、ザクとうふは売上の1%もなく「遊びの範疇」だそうです。メインのビジネスがしっかりしているからこそ、ザクとうふがつくれるわけです。
前橋市に本社を置く相模屋食料の創業は昭和26年。町のとうふ屋さんとして始まった同社が急成長を遂げたのは最近のことで、平成16年に32億円だった売上高が平成25年には157億円と、なんと10年もたたない間に5倍近く伸長しています。
こんな景気の悪かった時期に、デフレ商品のイメージがあるとうふでなぜこんなに成長できたのか?
その答えは平成17年に稼働を始めた日本最大のとうふ製造工場「第三工場」でした。6000坪の敷地に最先端の技術や設備を導入して全工程を機械化し、一日に100万丁ものとうふを生産する生産能力が相模屋食料を業界ナンバーワンに押し上げたのです。
ただし工場への投資額は当時の売上高を超える41億円という大勝負。しかも自動化を進めた巨大工場の運営はそれまでの業務の延長線上にはなく、取引先の生協から1000項目の改善を要求され、社員がみんないる前で怒られる等々、実際の稼働までは「壮絶な日々」だったそうです。
講演会ではこのあたりのお話を中心に、聞き手の秋山進氏の質問に鳥越社長が答える形で進行していきました。
◎雪印食中毒事件の渦中で気付いたこと
面白いポイントはたくさんあったのですが、そのなかの一点について記しておきます。
鳥越社長は年商30億円ほどの会社が40億円の資金を金融機関から調達して日本一のとうふ工場をつくったり、通常はあり得ないパッケージデザインであるザクとうふをつくったりと、かなりぶっ飛んだ構想を立て、普通なら相手から断られそうなことを実現してきました。
そこをどうやって突破してきたかといえば「熱意」で押すことで、何でも最初は断られるものだそうです(もちろん、熱意を裏付けるそれまでの実績もあるわけですが)。
凡人なら断られてしまえば凹むし、企画が無茶であるほど「そりゃそうだよな」と思うだろうし、取引先からみんなの前で怒られれば心折れそうなものです。でも熱意を失わず押していけるのは「メンツなどというものは初めからない」からで、そういう気持ちを持つようになったのは前職である雪印での経験がありました。
早稲田大学を出て雪印に入社した鳥越社長は当時、その経歴に誇りやプライドを持って働いていたそうです。しかし2000年に雪印は食中毒事件を起こし、鳥越社長はお客様への謝罪にまわり、多い時で1日に13回、土下座して謝りました。
そんな日々を過ごすなかで、鳥越社長は自分が拠りどころにしていた早大や雪印のブランドはしょせん、他人が築いたものだと気付きます。他人がつくった会社に乗っかって持っていた誇りは、会社がコケたらおしまい。でも、そういうものは初めからないと思うと、むしろパワーが出てくるようになると。
以下は鳥越社長の著書『「ザクとうふ」の哲学』(PHP研究所)から、関連する個所の引用です。
よそ様がつくってくれたものに乗っかって持っていたプライドや誇りは、よそ様がコケれば、それで終わり。むしろ「自分が誇っていいことなど、もともとなかったんだな」と思いました。自分が誇っていいのは、自分がやってきたこと、自分にできること、それだけです。このときから、私は入社後初めて、乳製品の製造法や安全について、自分で学び始めました。
(「ザクとうふ」の哲学』P57~58)
工場のみんながいる前でお取引様に怒られてしまうなんて、「メンツ丸つぶれだ」と思う方がいるかもしれません。
でも、メンツなどというものは初めからないのです。
雪印のときと同じです。自分たちが何をやっているか、何を実現したかが重要なのです。逆に、自分のメンツなどというものに縛られていたら、本当に見るべきものと向き合えません。
(「ザクとうふ」の哲学』P137~138)

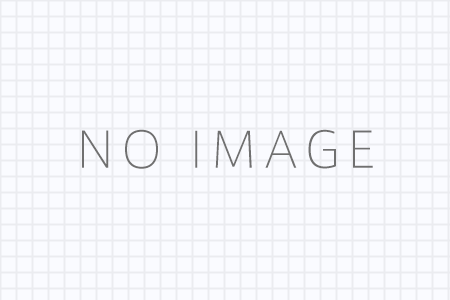



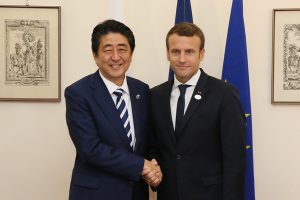

コメントを残す